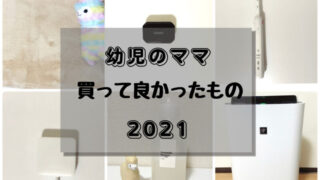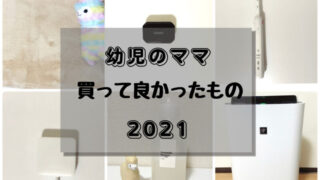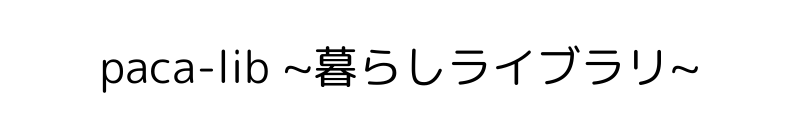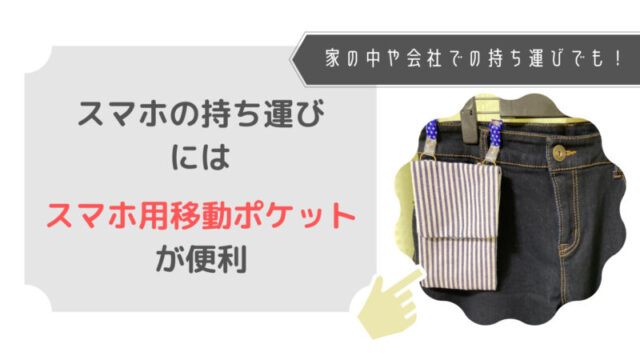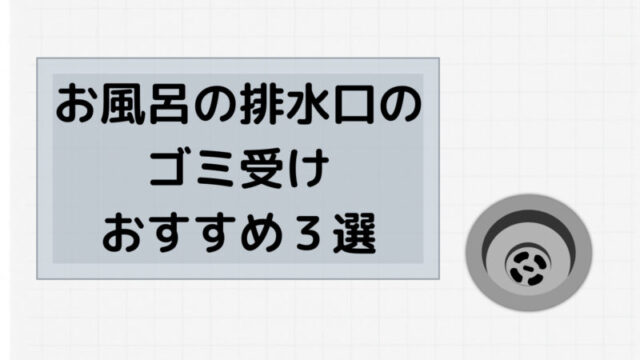念願のホットクックを買った!
これで毎日の献立はみーんなホットクックにお任せだ!わーい☆なんて思っていたんだけど、実際は煮物や蒸し物、煮込み料理しか作れていないなー。
ホットクック君、君はもっと高いポテンシャルを持っているはずなんだ。なのに、それを私は引き出せていない…っぐぬぅ。っと思っている方、いらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方に私が成る程こう使えばいいのか!と気付き、活用できるようになったきっかけとなった本と活用方法をお伝えしたいと思います。
先にささっと結論を書いておきますね。ズバリ、阪下千恵さんの料理本を購入し、その一冊にザーッと目を通したり、載っていたレシピを作ったりしていたら、その本の炒め物や麺物のレシピがとても作りやすく美味しかったので、その載っていたレシピを参考にコンロで火を使うレシピも少し分量を変えてホットクックで調理できるようになりました。(※PRではありません。)
ホットクックについて
ホットクックって?
ホットクックはシャープさんから発売されている”自動調理鍋”の家電です。知っている方はここは読み飛ばしてくださいね!
カットした具材と調味料を同時にいれて(料理によって自動でかき混ぜてくれる混ぜ技ユニットも最初にセットして)スイッチオン!すればあとは自動で料理を作ってるれる便利な調理家電です。
電気圧力鍋や炊飯器でおかずを調理するものとは決定的に違うところは
- 最初から調味料をいれて調理出来る※もちろんいれずに調理して後から調味料を入れて再加熱ももちろん出来る
- 圧力鍋と違って調理途中や調理直後でも蓋を開けて中を確認出来る。(炊飯器なら同じようにすぐに蓋を開けることは可能ですが、圧力鍋は名前の通り圧力がかかっているので圧力が抜けるまで鍋の中身を確認できません。)
- 鍋が勝手に混ぜてくれる!
というところだと思います。
ホットクックを購入しようか迷っているという方に「ホットクック買って良かったですか?」と問われたら、私は迷いなく「めちゃくちゃ良かった。もう手放せない。」と答えます。なんなら「惚れた。もう絶対逃してやれない。」なんてどっかええとこの御曹司みたいな事言っちゃいそうなくらい買って良かったなと思っています。
我が家のホットクックスペック
私が購入して使っているホットクックは”KN-HW24E-W“です。容量2.4Lの白色です。購入したのは2020年3月なので残念ながらステンレス内鍋のものです。2020年9月よりフッ素加工内鍋の物が販売されているので、これから購入する方はぜひフッ素加工内鍋の物を購入してくださいね。
実際ステンレス内鍋だとどう?かというと、いやーこびり付きますね(笑)取れないことはないんですよ?でも食洗機に入れて取れるかと言われたら、まー取れないです。手で少し力を入れて擦らないと取れないくらいはこびり付きます。それでもスイッチ入れて出来上がりまで火加減も調味もいらないという便利さを考慮するとまあしょうがないかなー。と思っていたのですが、2023年11月。フッ素加工内鍋、追加購入しました!
もうね、内鍋を洗い終わる時間が全然違う!一瞬。一瞬ですよ!スルッと汚れが落ちる。何を痩せ我慢していたのか。本当にもっと早く買っておけば良かった。という感じで快適です。
2021年9月に機能だけでなく見た目も新しくなった新型が発売されましたね!混ぜ技ユニットがさらに進化したモデルになっており、1.6L1タイプに新たなカラー “ブラック”が追加されました。
ホットクック。買ってすぐは煮る系のものしか作れていなかった。その理由
買う前はホットクックがあれば、主菜、副菜、汁物なんでも全部ホットクックで作ろう!うふふとか思っていました。ですがいざ買って使ってみて調理してみたら、なんでもは難しかった。
理由は以下のことが大きかったです。
ホットクックを使って加熱すると食材から結構な水分が出る
サバの味噌煮をホットクック付属のメニューからではなく(付属のレシピでは赤味噌が使われていて家に赤味噌なんてない泣となった)、ネットのレシピを使用して作ってみたら水分がたくさん出てタレがシャバシャバになってしまったりしていました。サバの味噌煮はフライパン調理と比べて食材の水分蒸発の割合が少ないだろうことは想定して少し調味料の水分は考慮して入れたつもりだったのですが、自分が考えているよりずっと食材からでる水分が多かったです。
あと、水分量の話とは少しずれるのですが、ブロッコリーとか蒸し調理してみたんですが(付属でついてきたメニュー集に基づいて調理しました)、加熱がおわってすぐに取り出して別容器とかに入れれば平気だと思うのですが、出来上がってしばらくそのまま放置してしまい、後から中をみてみたら火が通り過ぎでやわやわになり、色が火の通り過ぎでくすんでしまいました。
手動調理での加熱指定時間≠実際にかかる調理時間だから
ホットクック取り扱い説明書に書いてあるのですが、煮る、茹でる、蒸すの調理を手動で調理指定すると、まずホットクックの中のものが沸騰するまで自動で加熱が行われて、沸騰温度になってからこちらが指定した調理時間さらに加熱するようになっているそうです。なので”沸騰するまで”の自動加熱時間がよくわからないので、食材の火の通り加減が適当に時間指定すると結構火が通り過ぎてしまうことがありました。
要はホットクックにはホットクックの調理法が必要ということ
付属のレシピで作った、煮物、おでんやカレーなどは本当に簡単で美味しく作れて大満足。しかし炒め物や蒸し物などのレパートリーをもっと増やしたいと思い、フライパン調理のレシピを適当にアレンジして作ってみたらなんだかあまりうまくいかない。
買って少しの間使って私が得た結論はコンロや炊飯器、圧力鍋とも少しずつ違う、ホットクックさんにはホットクックさんのレシピが必要ということでした。(なんとなくさん付け)
ホットクックのおすすめレシピ本
そこでホットクックの本を購入しました。
そもそも時短したくてホットクックを購入したので、ホットクックのための調理法を自分で模索!なんてしていたら本末転倒になってしまうので、本屋さんに行ってホットクックのレシピ本をいくつか調べ、阪下千恵さんの”忙しい人のホットクックレシピ”を購入しました。(著者様twitterアカウントはこちら@chie_sakashita)
この本には色々な炒め物のレシピが載っていました。そして本屋さんでチェックして購入の決め手になったのが、私が普段使わない食材、調味料があまり載っていないことでした。日々毎日の献立をホットクックで作る参考書を探していたので、あまり使ったことのない食材や調味料を使用されるとそれをどう置き換えるのか?使わずに作るには?ということを試行錯誤しなければならなくなるので本を買う意味がなくなってしまいます。
本のレシピを作ってみた
本を購入し、”鮭のケチャップソース炒め”や”チャプチェ風野菜炒め”、”甘酢あん”、”ジャーマンポテト”などなど色々な炒め物レシピを作ってみましたが、どれも美味しかったです。あと、炒め物以外でも”煮崩れかぼちゃのクリームスープ”や”けんちん汁”などの汁物、”味噌煮込みうどん”や”具だくさんナポリタン”などの麺ものも美味しく作ることができました。本当に時間も気力もない時は”ミックスベジタブルとひき肉のスピードカレー”のレシピが子供用に具材を小さく切り分ける手間まで省けて本当に大助かりのおいしいレシピでした。
たくさん美味しく作れるレシピを作っていたら応用できるようになった
この本のレシピやホットクックの公式レシピをたくさん作って食べていて、同じような食材、同じような水分量になるおかずを見つけたら、「あ!本に載ってたあのレシピと同じような水(or酒)や片栗粉(小麦粉)の量にして作ったらうまくできるかも?」というように、他のコンロなどで作るレシピをうまく応用して作れるようになりました。
自分でオリジナルで考えたオリジナルレシピではないので分量や詳細は掲載できないのですが、”えのきと人参のきんぴら”や”豚肉の春雨入り韓国風炒め”、”鮭のちゃんちゃん焼き”などコンロで調理するレシピを具材の量、調味料の量を調整してホットクックで作っています。
ホットクックを応用レシピで使うときに気をつけている事
一番気をつけるべきこと
それは水分だと思います。電気圧力鍋なども同じことが言えるかもしれませんが、コンロで調理するのと違って水分が蒸発しないし、食材からたくさん水分が出るんです。これが美味しさの秘訣でもあるのだと思います。なので本や公式レシピを参考にレシピが出来上がった時の水分が似たレシピを参考に鍋に入れる水やお酒、粉類の量を決めて調理するようにしています。もし失敗して水分が多く出てしまったときは水溶き片栗粉を入れて再加熱!か離乳食用のとろみの素を入れてとろみをつけて調節しています(ほとんどこの方法でなんとなく解決できます笑)。
そのほかに意識していることは以下の2つです
・火が通りやすい食材と火が通りにくい食材を同時に入れるときはレンジで火が通りにくい食材を先に加熱して柔らかくしておいてから一緒に入れる。
・ステンレス内鍋なので内鍋に食材がこびりつきにくくするために水分がたくさん出る食材を内鍋の一番底に入れておく。
まとめ
ホットクック、購入したならできる機能を最大限に活用してたくさんホットいてクックしたいですよね。
私は阪下千恵さんの”忙しい人のホットクックレシピ”の料理本を購入し、本の中の炒め物や麺料理のレシピをたくさん作っていたら、応用で他の炒め物料理などでもホットクックを使って調理できるようになりました。
ホットクックで炒め物や麺ものなどをまだ挑戦できていない方、うまく活用できていない方の参考になれば嬉しいです。